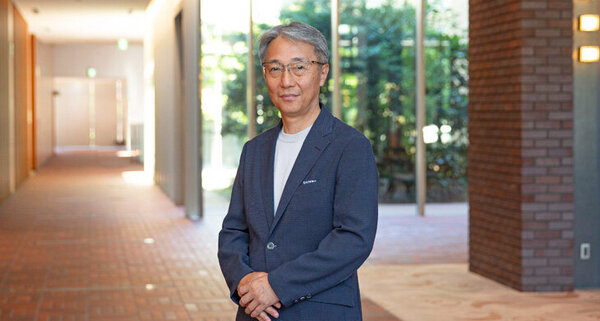
「地域と共に、次の20年へ」変わらぬ理念で進化を続ける西日本シティ銀行。
株式会社西日本シティ銀行
取締役常務執行役員 戸川 康彦
1990年、法政大学卒業後、株式会社西日本銀行(現:株式会社西日本シティ銀行)に入行。入行以来18年間営業店にて勤務の後、融資部(本部)を経て、日田支店長、天神支店長を歴任。2018年1月、人事部長に就任、2023年4月より人事担当役員として現在に至る。
※所属や役職、記事内の内容は取材時点のものです。
エンゲージメント向上に向けた20周年の取り組み。
旧西日本銀行と旧福岡シティ銀行の合併によって誕生した西日本シティ銀行は、2024年10月に発足から20年を迎えました。この1年間は、お客さまや地域の皆さまへ感謝をお伝えするため、さまざまなイベントを企画してきました。
アジア経済フォーラムではアジア開発銀行の総裁をお招きし、国際的な視点から地域経済を考える場を提供しました。また、地元企業や地域の魅力を発信する催しも数多く実施しました。
同時に、私たちが行内で直面したのは「職員のエンゲージメントをどう高めるか」という課題でした。外向けのアウターブランディングと職員に向けたインナーブランディングは表裏一体の関係にあります。
アウター施策ではCMシリーズ『銀行は、人だ。』を展開し、初期は人柄やサービス精神を描く内容でしたが、その次は『地域貢献は、人だ。』として、久山町の蜂蜜農園の実話を映像化しました。
地域を長年支えてきた姿をリアルなストーリーとして届けることで、地元の方々に誇りや親しみを感じていただいています。
一方のインナー施策としては、2024年11月に福岡ドームを丸ごと借り切り、職員やその家族5,000人以上が集まる大規模なグループフェスティバルを開催しました。
10周年時にも同じ会場で実施しましたが、今回は競技に加えてチーム対抗戦や交流プログラムを取り入れ、部署や世代を超えたつながりを生み出しました。
参加者からは「楽しかった」「当行の一体感を実感できた」といった声が多く寄せられ、愛社精神の高まりを強く感じました。
さらに『ブランチコミュニケーション』として、役員が176店舗すべてを手分けして訪問しました。私自身も10店舗ほどを回り、職員が当行の経営理念が育まれた歴史を知り、想いを共有してもらうために当行の歩みを紹介しました。
無尽会社として発足し、相互銀行、普通銀行への転換を経て西日本シティ銀行へと変遷する中で、一貫して中小企業の育成に尽力してきたこと、現在ではリーディングカンパニーとなった多くの企業を創業時から金融面で支え、地域の発展に尽くしてきた歴史を話しました。
こうした歴史を知ることで、特に若手行員には「この銀行で働く高い志と誇り」を持ってもらいたいと考えたからです。開催後のアンケート結果を見て大きな手ごたえを感じました。
育成改革と定着率向上。
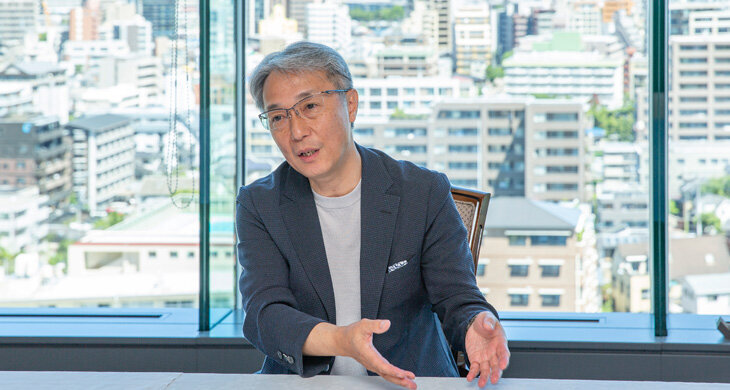
これらの取り組みを続けた結果、2024年度入行の総合職・地域総合職180名の学卒者は、1年半が経過した現在も離職者ゼロとなっています。
この数字は私たちにとって非常に大きな意味を持っています。
正直なところ、少し前までは離職率が全産業平均(3年で3割以上)と同等の時期もありました。その反省を踏まえ、現中期経営計画では育成制度を全面的に見直しました。
1年目は育成枠として集中的にトレーニングを実施し、基礎知識やスキルを固める。2年目でようやく独り立ちをさせ、5年目までは毎年集合研修を行って一体感や愛社精神を醸成する。
さらに、支店長や課長といったマネジメント層には360度フィードバックを導入し、部下からの評価とのギャップに気づいてもらう。加えて、1on1ミーティングの手法を標準化してコミュニケーションの質を高めました。
もちろん処遇改善も進めましたが、一番の課題は経営方針への共感や目的意識(経営理念に示された地域の発展に尽くすこと等)の理解・浸透が不足していることでした。
毎年実施しているエンゲージメント調査では、心理的安全性は非常に高い水準にあります。
しかし、当行や自身の将来に対する期待感が相対的に低位であり、当行で働く「誇り」や「自己効力感」を高めていく必要性を感じていたのです。
だからこそ、役員自ら店舗を訪れて理念や歴史を直接伝えることで、「ビジョンや価値観への共感」、「将来への期待や継続的な働き甲斐」といった土台づくりを行いました。
こうした取り組みを積み重ねてきた結果として、離職率は大きく改善しました。
今回の数字は新卒採用の実績ではありますが、キャリア採用で入行される方にとっても、より良い職場環境が整いつつあることをお伝えできると思います。
目的意識が育む長期活躍。
先日、キャリア採用で入行した方々を集めて懇談会を開催しました。その場でもブランチコミュニケーションの話に触れ、あわせて次のようなメッセージを伝えました。
「さまざまなバックグラウンドの経験やスキルを持つ皆さんには、スペシャリストとしての活躍を期待しています。さらには、当行の歴史や理念にも共感してもらい、その力を結集して地域を支えてほしい」と。
繰り返しになりますが、心理的安全性に加えて目的意識を持つことが重要です。同じ意識や想いを共有しながら働くことが、やりがいや高い志につながっていくと考えています。
ちなみに、キャリア採用を本格的に始めて7年になりますが、退職者は通算で1割程度にとどまっています。これまでに140名余りの方が入行し、現在も約130名が活躍しています。
これは当行の企業風土やカルチャーが着実に伝わっている証左であり、地道な取り組みではありますが、息の長い仕事や働き方に対する共感の表れだと感じています。
地域と共に歩む銀行のDNA。

当行には、商業銀行としてのDNAが深く根付いています。お客さまとの関係の深さは、他でなかなか真似できるものではありません。
その姿勢はグループの構造にも表れています。西日本フィナンシャルホールディングスは銀行を中核に、カード会社、証券会社、リース、IT、コンサルティングなど多様な事業会社が「並列」で存在しています。
これは、中小企業の成長を長年支えてきた歴史の中で自然と形成されてきたものです。
お客さまの経営課題はますます多様化しています。かつて事業承継といえば親族内が主流でしたが、現在では親族外承継、M&A、ファンドによる買収など、選択肢が大きく広がっています。
当行はこうした変化に対応できる体制を整備してきました。また、DXや業務改革においても、当行は「派手さより実効性」を重視しています。
たとえば、西日本シティ銀行アプリや新営業店システムは、当行がファーストユーザーとしてNTTデータと共同開発して地銀トップレベルのデジタル化を実現。
現在では同方式のバンキングアプリは全国30行以上に採用され、タブレットを利用した共同利用型の営業店システムは、銀行業界初のソリューションです。派手な存在ではありませんが、確かな成果を上げています。
当行では10年・20年先を見据えた息の長い取り組みや働き方ができます。こうした地道な活動こそが、お客さまとの長期的な信頼を築いているのだと考えています。
九州・福岡のポテンシャル。
福岡は今、「天神ビッグバン」や「博多コネクティッド」といった再開発プロジェクトが活発に進んでおり、約100棟のビルが建て替わります。
天神ビッグバンだけでも経済効果は約8,500億円、博多コネクティッドも5,000億円規模と試算されています。2040年までは人口増加が見込まれ、福岡都市圏全体では270万人規模に達する見通しです。
九州全体に目を向けると、半導体産業が非常に活発です。TSMC、東京エレクトロン、ソニー、SUMCO、ロームなどが相次いで設備投資を進めており、2021年から2030年までに70件以上、総額6兆円を超えると予測されています。
九州における半導体産業の最大の強みは、1,000社以上が関わるサプライチェーンであり、この規模は全国でも突出しています。
さらに、九州は豊富な水資源と安定した電源供給にも恵まれており、非化石電源比率6割超を誇る九州電力の体制はデータセンターの誘致にも直結しています。こうした条件が九州の将来性をより確かなものにしています。
進化を続けるために。

西日本シティ銀行は20周年を新たな出発点とし、地域とともに歩む姿勢をこれからもずっと大切にしていきます。
人材育成やエンゲージメント向上への取り組みを一層強化し、職員一人ひとりが誇りとやりがいを持って長期的に活躍できる環境を整えていきます。
変化の激しい時代にあっても、私たちの原点は「人」と「地域」です。地道な努力の積み重ねによって信頼を築き、福岡・九州の未来を切り拓いていきます。
そうした思いを体現する取り組みの一つが、本店ビルの再開発です。現在、博多駅前にある本店ビルと別館、事務本部の3棟を9年間かけて連鎖的に建て替えており、「博多コネクティッド」の中でも目玉のプロジェクトとなっています。
新本店は地上14階・地下4階の規模で、現在の本店の3フロア分が1フロアに収まるほどの広さを備えます。
駅前には大きな屋根付きのイベントスペースを設け、博多駅からキャナルシティまでの回遊性を高めるとともに、地下には音響にこだわった400席規模の「NCBホール」を整備してコンサートや演劇、地域イベントに開放します。
まだまだやるべきことは多くありますが、「足りない」と感じ続けることこそが進化の原動力だと考えています。
足りていると思った瞬間に成長は止まる。理念を共有し、高い志を持った仲間とともに、この街と次の20年を歩んでいきたいと思います。



